キャンパスライフ
Campus Life

Campus map
キャンパスマップ
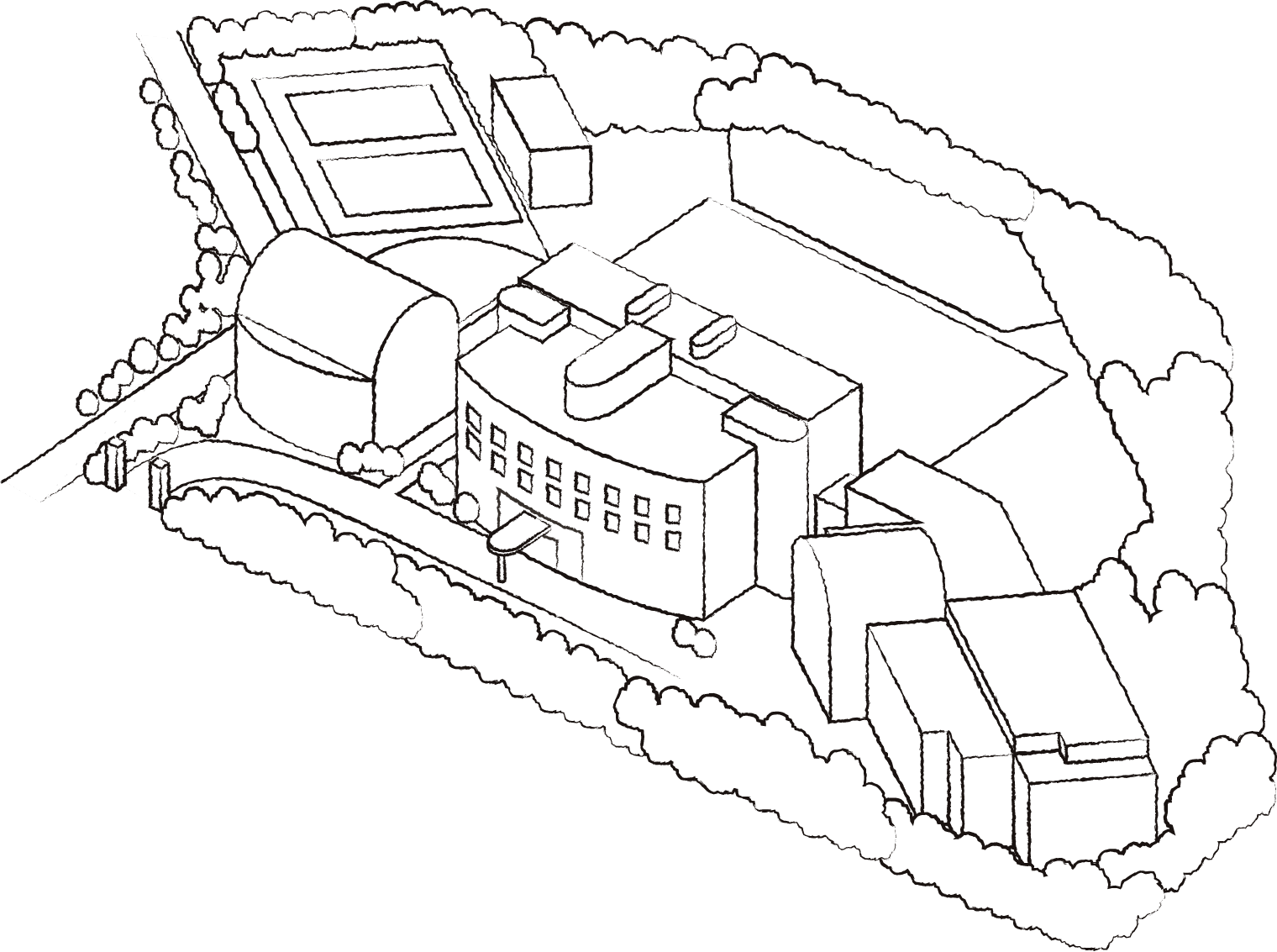
Campus calendar
キャンパスカレンダー


帝塚山学院大学には、友だちとの絆を深め、共に成長できるイベント・行事が盛りだくさん!
さまざまな経験を通して得た出会いや発見は、人間的な成長にもつながります。
大切なのは、積極的に参加し、思いっきり楽しむこと。
それが、キャンパスライフをいっそう彩る一歩になります。

Dining
ダイニングコモンズ(学生食堂)
全国初の学生運営食堂!
「食を通じて、おいしく楽しい、心身ともに健康な生活を実現すること」を目的に、食環境学部がプロデュース。専属の管理栄養士と学生が運営しており、様々なアイデアを取り入れながら運営を行っています。

Library
ナレッジコモンズ(図書館)
書籍、DVDなどのあらゆるメディアが揃う従来の図書館をリニューアルし、個人学習やグループ学習ができるスペースも充実する「ナレッジコモンズ」に。知的好奇心を刺激し、幅広い学びの場となっています。


Photo Snap Collection
ファッションスナップ
おしゃれな在学生のスナップショットをご紹介!
ファッションポイントや大学生活のマストアイテムなどをQ&A形式で掲載しています。



